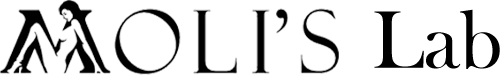ウエディングドレス姿のヤオの優しい告白
共有
撮影が終わって休憩に入ると、私は彼女が待っている更衣室へ向かった。撮影中、ヤオはテーマに合わせて本物そっくりのシリコンマスクをかぶっていた。完璧な変装で、彼女はまるで別人のようにも見えた。彼女の手には光沢のある白いサテンの手袋がはめられ、ウェディングドレスにエレガントな雰囲気を添えていた。
「ヤオ、入ってきます。」

私はドアをノックして中に入ると、そこに彼女がいた。純白のドレスを着て、マスクを顔につけたままだった。手袋をした手は軽く膝の上に置かれていた。
彼女は私の存在に気づき、いつもの温かい笑顔で私に挨拶した。それでもマスク越しの笑顔だった。
「プロデューサーさん、どうでした?」
「まあ…もちろん…」
彼女の驚くべき美しさは、変装の裏に隠れていても、私に適切な言葉を見つけられなかった。
「いや…あの…君は本当に美しいよ。」
「へへ、ありがとう!」
「いや、本当ですよ、あなたは世界で一番美しい花嫁ですよ!」
それは自分でも恥ずかしいセリフでしたが、正直な気持ちでした。
「うふふ、褒められすぎて顔が赤くなっちゃうよ~」手袋をした手で頬を撫でる。

「でも、そう言っていただけると本当に嬉しいですよ、プロデューサーさん」
彼女は頬に手を当てた。マスクのせいで赤みや表情は隠されていたが、声のトーンにはかすかな孤独とためらいが感じられた。
「あの……ヤオ?」
「はい?何か問題でも?」
「何か心配なことあるの?」
彼女の態度には暗い影が漂っていたので、マスク越しでも思わず尋ねてしまいました。
彼女は少し驚いた様子でこう言いました。
「ああ、どうやってそれを理解したの?」
「だって、ヤオ、君のことなら何でも話せるんだから。」
「……私ってそんなに簡単に読めるの?」
「はい、とてもそうです。」
「うわぁ…プロデューサーさんって意地悪ですね」
彼女が大げさに頬を膨らませて口を尖らせ、サテンの手袋がドレスに少しだけ触れているのを見て、私は苦笑いすることしかできなかった。

「それで、何が起こっているんですか?」
「このウェディングドレスを着て、自分の将来について考えるようになりました…」
「あなたの将来は…?」
「運命の人を見つけても、一緒にいられないかもしれないと思うと、少し不安になりました。」
「ハハ、それについては彼を見つけてから考えればいいよ。」
「もしすでに彼を見つけてしまったらどうしよう?」
「あー…そうですね…」
私たちの間に気まずい沈黙が訪れた。
「ごめんなさい、困らせてしまったね?」
「全然。どんな男でも君と一緒なら幸せになれるよ、ヤオ。」
「ふふ、またそんなこと言ってるのね…」
「でも、それは真実です。」
「では、たとえ大きな障害があったとしても、あなたはそれを乗り越えて愛する人と一緒になれますか?」
「もちろんそうしますよ。」
"本当に?"
"本当に。"
再び重苦しい沈黙が更衣室を満たした。
それから、彼女はマスクを破って話し始めました。彼女の目は、マスク越しでも感じられるほどの強さで私に釘付けになりました。
「ありがとう。そう言ってくれると安心します。」彼女は少し間を置いてから、サテンの手袋をはめた手を伸ばし、本物のマスクを慎重に外すと、彼女の素顔が現れた。柔らかく、親しみやすく、息を呑むほど美しい。「プロデューサー、私からあなたに伝えたいことがあります。私の運命の人はあなたです。」

"…はぁ?"
彼女の突然の告白で私は頭が真っ白になった。
「プロデューサーさん、結婚を前提に私と付き合ってください」
彼女は私の目をまっすぐに見つめ、無防備で真剣な素顔で私を言葉を失いました。
「プロデューサーさん、結婚してください。」
突然の提案で私の脳はほぼショートしそうになった。
私は混乱した心の中で、どう返答するかを必死に考えました。
しかし、いくら考えても明確な答えは出てきませんでした。
「は、はい、喜んで!」
私がどもりながら返事をすると、彼女は私の手をしっかりと握り、サテンの手袋が私の肌に冷たく感じられた。
「プロデューサーさん、大好きです!」
彼女は輝く笑顔で私に腕を回し、私は優しく彼女を抱きしめ返しました。
ヤオの温もりを感じながら、私は幸せに浸りました。

彼女の存在が心地よかったのかもしれないが、私はより穏やかになり、頭がはっきりしてきたように感じた。
すると突然、二つのふっくらとした乳房が私に押し付けられるような柔らかい感覚を感じた。
(ああ、やばい…これはまずい)
彼女の胸は我が社で最も印象的な胸の一つであり、私の胸に押し付けられ、私の理性を脅かした。
「プロデューサーさん、好きです…」
(だぁぁぁ!)
彼女が耳元でささやくと、私の心臓はさらに激しく鼓動した。
そして当然のことながら、血が下へ流れ落ちました…
「あれ?なんか硬いものが押し付けられてる感じがする……?」
ヤオは不思議そうな表情で下を向いた。
「きゃあああ!?」
彼女は悲鳴を上げて私を突き飛ばし、私は床に倒れた。
「あ、ごめんなさい……びっくりしちゃった」
彼女は私のズボンの中のテントを見て顔を赤くし、手袋をした指を少しそわそわと動かした。
「いや、謝るべきは私だ…」
この状態では普通の会話ができる自信がありませんでした。
「仕方ないだろう? 男なんだから」
「恥ずかしいです…えっと…ヤオが本当に素晴らしいから…」
彼女は私をかばおうとしたが、私には言い訳をつぶやくことしかできなかった。
「へへ、ありがとう。」
彼女が笑ったときの天使のような笑顔は息を呑むほど美しかった。
「プロデューサーさんは私のこと好きだからこうなったんでしょ?」
"はい…"
私は情けない気持ちになりながら、弱々しくうなずくことしかできませんでした。
「他の女の子とはこんな風にはならないよね?」
「いや……それはヤオ君だからだよ」
私は必死に首を横に振った。
「ああ、それは嬉しいよ!」
そう言うと、ヤオは私の下腹部に手を伸ばし、サテンの手袋で私のシャツを撫でた。
「それなら私が責任を取らないといけないですよね?」
"はぁ?"
「それでは…私が対応させていただきます。」
そう言うと、彼女は落ち着いて私のベルトを外し、手袋をした手を器用に動かしながらズボンを下ろし始めた。
「ちょっと、ヤオ!?」
私は慌てて止めようとしましたが、抵抗はむなしく、すぐに下着姿になってしまいました。
「ふふ、これも脱ぎましょう。」
「いや、やめて――」
ヤオの手は私の下着も剥ぎ取り、彼女のサテンの手袋の滑らかな感触が私の肌に触れるのを感じました。
「わぁ…これがプロデューサーさんの…」
完全に勃起した私のペニスが飛び出すと、彼女は小さな叫び声を上げました。
「あの…あまり見つめないでくださいよ…」
「なんでダメなの?すごくかわいいから。」
「いや、恥ずかしいです…」
「うふふ、大丈夫ですよ。私も同じです。」
彼女は顔を赤らめながらも、私のペニスを興味深そうに観察していました。
それは完全に勃起して私のお腹に押し付けられていましたが、明らかに平均よりも小さく、先端まで包皮で完全に覆われていました。
愛する人にこんな幼稚なペニスを見られるなんて、恥ずかしくてたまらなかった。
彼女がそれを「かわいい」と言ったことで、私の劣等感はさらに強くなった。
「プロデューサーのペニスは包茎ですよね?」
彼女の言葉を聞いて、私は恥ずかしさで顔が赤くなった。
「変…ですか?だって…小さいし…」
「いいえ、かわいいし素敵だと思います。」
「かわいい?」
「はい、とてもそうです。」
「そ、それはよかった……」
彼女はおそらく私を褒めようとしていたのでしょう。そう考えると、私は自分の小さな息子を少し誇らしく思いました。
彼女はためらいながら、サテンの手袋をはめた指先でペニスの軸を突いた。その滑らかな生地に私は身震いした。
「ペニスの大きさはよく分からないけど、すごく硬くて温かい…」
「あぁ……」
「あの…ペニスは硬さが大事だと聞きました。」
「あ、本当ですか…?」
「それで、あなたの作品はすごいと思いますよ、プロデューサー。」
「ま、本当ですか!?」
彼女の賞賛は私の気分を高揚させた。
しかし次の瞬間、私は現実に戻った。
「だから、少し小さいことは全然問題じゃない。そして、私は気にしない。」
(ああ…彼女に私を安心させなければならないと感じさせてしまった。)
彼女は私の気持ちを傷つけないようにそう言ったに違いない。
しかし、その優しさは私の心をさらに深く傷つけるだけだった。
(それでも、ヤオの気持ちは嬉しかったです。)
それで勃起が治まりませんでした。
「とても活気があって素敵ですね。」
彼女は愛情を込めて指で輪を作り、サテンの手袋を私の肌の上を優しく滑らせながら撫でました。
「くっ……」
「ふふ、かわいい声だねぇ。」
それは彼女の手の中でピクピクと動いた。
「気持ちいい?」
「はい…とても…」
私が正直に答えるのを見て、彼女は微笑みながらゆっくりと手を上下に動かし始めました。
「どう?痛かったら言ってね?」
「あ、大丈夫ですよ…」
彼女は包皮の上から触っているだけなのに、まるでセックスをしているような気分でした。
彼女の手袋をした指先が亀頭に触れるたびに、甘い痺れが私の体中に広がった。

「ん……」
「騒いでも大丈夫だよ」
「はい…自分でやるよりもずっと気持ちいいです。」
「プロデューサーさんもこういうのは初めてですよね?」
彼女は嬉しそうに微笑んだ。
「じゃあ今日はいいこと教えてあげなきゃね」
すると、ヤオは動きを速めた。
包皮が剥がれ、隠れていた先端が現れた。
「へへ、きれいなピンク色だね。」
そう言うと、彼女はサテンの手袋をはめた指をその部分に押し当てた。滑らかな生地がその感覚を強めた。
「ひゃあ!?」
敏感な箇所への刺激で声が出てしまいました。
「ああ、ごめんなさい。びっくりさせちゃったでしょう?」
彼女は謝ったが指を離さなかった。先走り液のかすかな光沢が彼女の手袋に付着していた。
彼女の指先から出る透明な液体の糸を見て、私は興奮を抑えることができませんでした。
先端に透明なビーズが膨らんでいました。
「じゃあ、これを試してみましょう…」
ヤオは左手で僕のペニスを支え、右手の親指と人差し指で亀頭を刺激した。サテンの手袋がかすかに光っていた。
「あぁ……あぁ……」
あまりの快感に声を抑えることができませんでした。
「どんな感じ?いい感じ?」
「はい…すごいですね…」
彼女は手を動かすのを止めなかった。
むしろ彼女はスピードを上げて、その感覚を強めた。
「あぁ…ダメ、八百!イっちゃう!!」
彼女が絶頂を迎える直前になんとか止めることができました。
それ以上だったら、間違いなく射精していたでしょう。
彼女は少し不満そうに立ち止まったが、すぐに何かを思いついたかのように微笑んだ。
「包皮を剥いてみましょうか?」
「待って、待って――」
「もちろん、やろうよ…」
私のためらいを無視して、ヤオは手袋をした指で包皮の先端を掴み、一気に引き下げた。
「あ!?」
軽い痛みが襲い、続いて亀頭が空気にさらされた解放感に襲われました。
「ふふ、もう全部剥がれちゃったよ。」
満足した彼女は再び私のペニスに手を伸ばしました。
彼女はサテンの手袋を滑らかに滑らせながら、露出したばかりの部分を優しく愛撫した。

「わぁ…ピンクがさらに濃くなったね。」
「ヤオ、待って…」
彼女は何も答えず、亀頭全体を優しく撫でた。
「はぁ…はぁ…」
「ふふ、呼吸が荒くなってきたよ」
彼女が言った通り、私の呼吸は大きく荒くなっていた。
私は人生でこれほど性的に興奮したことはありませんでした。
「イキたいんでしょ?」
「えーっと…あの…」
「恋人の前で恥ずかしがる必要はないよ。」
「はい…したいです…」
私の話を聞いて、ヤオは微笑んだ。
「ふふ、私の手にたくさん出してください!」
彼女は両手で筒を作り、サテンの手袋で私の亀頭を包みました。
これまで包皮を使ってしか自慰行為をしたことがなかった私は、本能的にひるんでしまった。
「前よりもさらに気持ちよくなるよ。」
「待って…待って…」
「大丈夫だよ、怖がらないで。」
ヤオの目を見ると、妙に安心した。
彼女の手袋の滑らかな質感が、私の露出した亀頭と陰茎を包み込んだ。
「ゆっくり…優しく…」
彼女は手を上下に動かし始めた。
「うぅ……」
「気持ちいい?」
「最高…最高…」
今までに経験したどんな快感よりも気持ちよかった彼女の手に身を委ね、私は容赦なくうめき声をあげた。
「大丈夫だよ。いつでもイキたい時にイっていいよ。」
「はい…ありがとうございます…」
私にできることは、感謝の気持ちを小さく言うことだけだった。
「あなたのペニスはちょっと臭いわ。私たちのために一生懸命働いてたから、洗う暇もなかったのね?」
彼女はそう言いながら優しく微笑んだ。
「ごめんなさい、汚くて…」
「いいえ、それはあなたの努力の証です、プロデューサー。」
そう言うと、彼女は僕の亀頭に顔を近づけました。
「やお!?」
「すごくいい香りがするよ!」
彼女が何度も嗅ぐのを見ていると、私のペニスにさらに血が集まってきた。
「あぁ……」
「ふふ、また大きくなったよ。」
「ヤオ君は素晴らしいから……あぁ……」
「へへ、ありがとう。」
彼女の手の中でそれがさらに硬くなっていくのを感じました。
私は息を切らしながら、何度も自分の気持ちを彼女に伝えた。
「ヤオ…好きだよ…愛してるよ…」
「私もプロデューサーさんが大好きです…」
「ああ……」
彼女は幸せそうな表情で手を動かし続けた。
「ヤオ、あなたは世界で一番美しくて、可愛くて、素晴らしい女性です…」
「優しくて、かっこよくて、それでいてとっても可愛い、プロデューサーさんは私の運命の人です。」
彼女の言葉一つ一つが私を喜びで満たし、私のペニスはさらに膨らみました。
彼女の手の動きが速くなった。
お互いの気持ちを確認し合いながら、私たちは行為にさらに深く入り込んでいった。
「やお…もう…イキそう…」
高まる快感に耐えきれず、もう限界でした。
「遠慮しないでください」
彼女は動きを激しくして、私に射精を促した。
クライマックスへの前兆を感じました。
とろけるような快楽の波が私の睾丸から湧き出て、尿道に集まりました。
「あぁ……あぁ!!」
「さあ、たくさん出して。」
彼女の手が私の亀頭を撫で、彼女の指先が私の陰唇小帯を刺激し、彼女の手のひらが私の陰茎を擦り、そして何よりも、ヤオの存在そのものが私を高揚させた。
「やお!イっちゃう!うっ!」
「そうだ、全部吐き出せ」
彼女は手を止めず、サテンの手袋で私をさらに誘い続けました。
彼女の温かい手に包まれ、亀頭を愛撫され、敏感な部分を刺激されて…
「うわあ!! 来るよ!! あああ!!」
ジュルジュルと音を立てて、精液が彼女のサテンの手袋の上に勢いよく飛び散った。
「あ!あ!あ!あああ!」
私は彼女の白い手袋の上に自分の欲望を次々と放出した。
それは、一人で自慰行為をしたときに感じたどんな快感とも比べものにならないほどの快感でした。
私がイッたとき、腰が制御不能に震えました。
「うわぁ…まだ来てる…」
「はぁ……はぁ……ごめんなさい、いっぱいイっちゃって……」
脈打つたびに先端から濃厚な精液の塊が飛び出し、手袋を汚した。
ヤオは私が終わるまでしっかりと私を抱きしめ続け、彼女のサテンの手袋は私が解放されたことで滑りやすくなっていました。
「へへ、よく来たね。」
「ありがとう、ヤオ…」
彼女はそれを見て微笑んだ。
「気持ちよかった?」
「はい、とても…」
「プロデューサーさんが気持ちよくなってくれて本当に嬉しいです…」
ウェディングドレスを着た天使が私に微笑みかけ、サテンの手袋をはめた手から黄色がかった精液が滴っていた。
その倒錯した光景に私は興奮しすぎて気を失いそうになり、彼女の汚れた手袋の上に少し漏れてしまいました。
もう一つの汚れが布地全体に広がりました。
「あ、あの……すみません……」
「大丈夫、予備はあるから。」
そう言うと、彼女は手袋をした手から少し舐め取った。
「ほら、プロデューサーさんの精液って美味しいよ…」
彼女は話しながら、残留物で光っているサテンの手袋を私に見せました。
「ん…ずるずる…パンパン…ゴクゴク…」
彼女はその粘液を吸い上げて飲み込んだ。
「はい、すべてきれいになりました。」
「はは、そうだね。」
どれだけ興奮しているはずだったのに、圧倒的な快感で私のペニスは完全に萎えてしまっていた。
「あなたのペニスも満足しているようですね。」
ヤオは、私の今や萎え、包皮で覆われた「象の鼻」を見て、くすくす笑いながら、手袋で軽く撫でた。
「今日はこれで終わりにしましょうか?」
彼女はタオルで私の下半身を拭いてくれました。
「ありがとう……あの……ヤオ……」
「はい、何ですか?」
私は恥ずかしさで顔を赤らめながら、「もしよかったら、もう一回してほしいんですけど…」と言って彼女の目を見つめました。
「へへ、もちろん大丈夫ですよ」
そう言うと、ヤオはサテンの手袋をはめた手を私の頬に置き、軽くキスをした。大量の精液を飲み込んだばかりなのに、彼女の唇は驚くほど甘かった。
「次回はもっと気持ちよくしてあげるよ。」
"はい…"
ヤオは私に優しく微笑み続けた。
もう一度抱き合った後、彼女はテーブルの上の本物そっくりのマスクに手を伸ばして顔に戻し、手袋をした手で調整して、再び撮影で演じていた役柄に変身した。彼女はふざけてウインクしながら、「仕事に戻って、プロデューサー」と言った。

そして、撮影現場に戻りました。