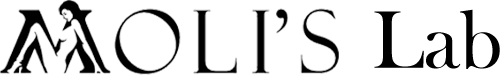仮面女子との生活(第1話)
共有
「イーサン、君は今年の会社の会議に出席するよ。上層部は君に報告をさせようとしているから、しっかり準備しておいて。時間になったら一緒に来てくれ」上司のトニーが私の肩を強く叩きながら言った。
「わかった。準備はできている。偉大なリーダーには弱い兵士はいないということを本部の連中に証明する時だ!」私はニヤリと笑った。
トニーは私をにらみつけた。「本部にいるときは、うぬぼれた態度はやめなさい。前回の昇進で失敗したのも、あなたの態度のせいです。」
彼は少しためらい、意味深げな表情でこう付け加えた。「次男がもうすぐ生後1ヶ月になります。」
私はその言葉に少し考えました。そしてうなずきました。トニーは私が入社してマーケティング マネージャーに昇進した頃からずっと私の指導者でした。彼はこの支店だけでなく、他の部署も統括するのに十分な資質を持っていました。会社は彼を家族がいるシカゴの本社に転勤させることを検討しており、彼は私を後任として推薦してくれたのです。
しかし、さまざまな理由から、私はその仕事を得ることができませんでした。おそらく、私の心のどこかで、彼に辞めてほしくなかったのでしょう。いずれにせよ、私は彼を自分の足で引きずり下ろしてしまったのです。
彼はオフィスのドアのところで時計を叩き、「あまり遅くまで残らないで。早く帰ってください」と言った。
私は彼が去るのを見送り、その後さらに数時間滞在してレポートを仕上げました。最後に、コンピューターをシャットダウンして出発しました。
入り口に着くと、雨が降っていることに気づいた。私はオフィス近くのファストフード店で夕食をとることにした。独身なので、食事だけを気にすればよい。食事を終えると雨が止んでいたので、少し散歩してみることにした。
ちょうどそのとき、家主のスミス氏から電話がありました。今夜、購入希望者が私の家を見に来るのですが、彼は町を離れているので、私に対応を頼みました。私は、この荒れ果てた家を売るのは恥知らずだ、誰が買ったとしても、そのまま解体業者に引き渡したほうがましだと冗談を言いました。彼はただ笑って、買い手の情報を私に送ってきました。ローラさん。午後 8 時 30 分。時間を確認すると、あと 20 分。まともに歩くには時間が足りないので、代わりにタクシーを呼びました。
交差点に着くと、突然赤いバイクが私の目の前で急に止まり、泥水がズボン全体に飛び散りました。最高。これを履いて4日目にして、今度はこうなりました。
最初に話しかけてきたのは若い女性の運転手だった。「ああ、大変!ごめんなさい。急いでいたので間に合わなかったの。ねえ、タイムズスクエアへの行き方知ってる?」
私は振り返って彼女を見た。彼女は全身黒ずくめだった。ニーハイブーツ、革のパンツ、革のジャケット、手袋、フルフェイスのヘルメット。肌は1インチも見えなかった。ヘルメットの下から茶色の髪がはみ出ていた。
彼女は現金を取り出しました。「これ、ドライクリーニングに出して。私のせいよ。」
私はあざ笑った。「お金の問題じゃない。でも、この手作りのイタリアのデザイナーズパンツの代償を払うなら、300ドルでは足りないよ。とにかく、今はタクシーを見つけるのが難しい。タイムズスクエアは信号2つ先にあるから、右に曲がるんだ。私は近くに住んでいるから、乗せてあげようか?」
返事を待たずに、私は彼女のバイクに飛び乗った。
彼女は驚いたようでしたが、予備のヘルメットを私に手渡しました。「ちょっと待って。」
それを固定した瞬間、エンジンが唸りをあげた。私は本能的に彼女の腰に腕を回した。
彼女のジャケットに触れた瞬間、彼女は感電したかのように固くなりました。そして、ドカンとブレーキを踏みました。私のヘルメットが彼女のヘルメットにぶつかり、頭がぶるぶるしました。
「手を出さないで!バイクにちゃんと座れない男なんて、どんな男?」と彼女は怒鳴った。
「えっと、あなたが飛び立ったとき、私はまだきちんと座ってもいなかったのに!あなたはスタントライダーか何か?」と私は言い返した。
「もう大丈夫ですか?」
「ああ」私は自分の気持ちを調整しながらつぶやいた。
5分後、私たちは私のアパートに到着しました。足は冷たくて濡れたズボンのせいで完全にしびれていました。左足を自転車の上に振りかざしたとき、凍り付いた手足が動かなくなり、私は顔から舗道に倒れ込みました。
バイカーの女の子は息を呑み、急いでバイクから飛び降りた。「大丈夫?」
女の子の前で転ぶなんて、屈辱的だ。だから起き上がる代わりに、大げさに仰向けに転がった。「気にしないで。愛国心を表現しただけ。祖国の地面にキスをしただけ。」
そして、ヘルメットを彼女に渡し、膝をさすりながら歌い始めました。
彼女は黙ったまま、自転車を取りに行きました。私は彼女を見て、ようやく気が付きました。彼女は素晴らしい体型をしていました。身長は170センチはあり、ブーツを履いた脚は長く、ウエストは細く、革のジャケットはあらゆる部分を強調していました。彼女の体がこれほど素晴らしいのなら、どんな顔を隠しているのでしょう。
好奇心は猫を殺す。私は急いで立ち上がり、彼女の自転車を手伝った。
彼女はニヤリと笑った。「あなたの愛国心はどうなったの?」
私は両手をこすり合わせた。「1日2分で十分だ。それ以上だと風邪をひいてしまうかもしれない。それに、女性を自転車で苦労させるなんて、愛国心がない。」
彼女はその話題を押し付けることなく、うなずいた。
私は彼女がバイクを駐輪場まで押すのを手伝いました。彼女は私にお礼を言い、私に出て行っていいという合図をしたようでした。私は彼女のヘルメットから目を離しませんでしたが、彼女は気にしませんでした。彼女は素早くヘルメットを脱ぎ、私は彼女がヘルメットの下に顔の大部分を覆う黒いマスクを着けていることに気付きました。私が見分けられたのは、彼女のあごのラインがはっきりしていることだけでした。
紫色のアイシャドーを塗った彼女の目は瞬きしながら私を見ていた。彼女のまつ毛は長く、瞬きしても動かないまつ毛もあるようだった。それが彼女の外見への私の興味をさらに掻き立てた。
彼女は真剣な顔で私を見て言いました。「今日はありがとう。パンツを汚してしまってごめんなさい。まだ誰かを探しているから、もう迷惑はかけないわ。」
長居する理由はないとわかっていたので、「大したことじゃないよ。全然気にしてないよ。先に行ってください」と言った後、私は振り返って建物の中に入っていった。
ちょうど立ち去ろうとしたとき、電話が鳴った。知らない番号だった。
「もしもし?誰ですか?」
「イーサンさん?ローラです。スミスさんと家について話しました…」その声は彼女のものだった!
私は振り返った。彼女は驚いて私を見ていた。
私はくすくす笑った。「まあ、世界は狭いですね。」
彼女は軽く手を振った。
トニーが私を会社に引き入れてから、私はほぼ 4 年間この家を借りていました。アパートにはエアコン、インターネット、ガスなどの設備が整っていて、家賃は安く、3 ベッドルームの部屋で月額数百ドルでした。スミス氏は 2 年前にデトロイトに引っ越しましたが、それ以来新しい入居者はいませんでした。他の入居者が徐々に去っていく中、独身でここに住み続けるのは私だけでした。昇進を無事に勝ち取った今、市の中心部に引っ越す時が来ました。
道中、私たちは何気なくおしゃべりをしましたが、彼女はあまり話好きではないようでした。私が得た唯一の情報は、彼女の名前がローラだということだけでした。
到着すると、私はドアを開けて電気をつけました。入り口に立って、歓迎のしぐさをし、彼女にスリッパを手渡しました。彼女は玄関でためらいながら、「靴を履いたままでいいですか?このブーツは脱ぐのが面倒なんです」と尋ねました。
私は彼女の黒いニーハイブーツを見て、彼女のジレンマを理解したが、彼女の言うことには従うつもりはなかった。「でも、掃除が面倒だし、外はちょうど雨が降っていたところだし。」そんなに面倒なら、そもそもなぜ履くのだろう?
彼女はうなずいて中に入った。ドアを閉める前に最後にもう一度外を見て、しぶしぶブーツを脱ぎ始めた。
私はソファを指差して「着替えてくるから、座って」と言った。私がリビングルームのエアコンを30度に設定してスイッチを入れると、彼女はうなずいた。私はウォーターサーバーもつけた。本当に寒かったからというだけでなく、彼女にマスクを外してもらい、ようやく彼女の顔が見えるようになるためでもあった。
私はほんの数分でいつもの部屋着に着替えた。厳密に言うとパジャマだった。そしてリビングに戻った。彼女はまだマスクを着けたままソファに座っていた。ブーツの下には膝上丈のジョッパーズを履いていて、膝から下は厚手の肌色のストッキングを履いていた。彼女の脚は相変わらず細かった。
私は彼女に熱いコーヒーを一杯淹れてあげました。「さあ、アラビカコーヒーをどうぞ。これは去年中国旅行から持ってきたもの。最高級のコーヒーの一つよ!」と誇らしげに言いました。
彼女は不思議そうな顔をして、「え?中国産のアラビカコーヒーなんて聞いたことないわ。」と言いました。
「そう?ははは、まあ、中国産のこのお茶はどこよりも美味しいよ。熱いうちに飲んでね。」私は期待しながら彼女を見た。
彼女はカップを取ろうと手を伸ばしたが、すぐにコーヒーテーブルの上に置いた。「喉は渇いていないわ。今からアパートを見せてもらってもいい?」彼女の目的は明らかだった。
諦めきれず、私は再びコーヒーを手に取り、「急がなくていい。まずは一口飲んで。アパートは広いから、ゆっくり見て回った方がいいよ」と言いました。私はカップを彼女のほうにそっと押しました。彼女は断ろうとしましたが、その途中で誤ってカップを倒してしまい、湯気が立つコーヒーが手袋をした手にこぼれてしまいました。お湯はちょうど沸かしたばかりだったのです!
「あ!大丈夫ですか?」びっくりして、心配して急いで彼女の手を握りました。彼女は何も言わず、ただ首を振るだけでした。革手袋のおかげで火傷はしていませんでした。
まだ心配だったので、私は本能的に彼女の手首をつかみ、彼女が反応する前に手袋をはぎ取った。彼女は抵抗しているようだったが、明らかに私ほど強くはなかった。
私は手袋をテーブルに放り投げ、彼女の手をかざしてよく見てみた。私は驚いた。彼女の手には爪がなく、その手触りは彼女の足に履いている肌色のストッキングとまったく同じだった。しかし、彼女の手は乾いていた。熱湯で火傷したわけでもなかったのだ。
私は凍りつき、彼女の手を見つめた。彼女は素早く手を引っ込めて、きつく言った。「コーヒーはいらないって言ったでしょ! 大丈夫だって言ったでしょ! どうしてそんなにしつこく言うの?」
彼女は、私が強く掴みすぎておそらく傷つけたであろう手首をこすりながら、マスクをした顔に警戒心の強い目を浮かべていた。
「あ…ごめんなさい。もし大丈夫なら、アパートを見に行きましょう。」 突然、この女の子がとても奇妙で、また興味深いと感じました。
彼女の首の皮膚が手や足の皮膚と合っているように見えることに気付き、私はためらいながら「手袋はスーツとつながっていますか?」と尋ねました。しかし、私はすぐにその質問が不適切だと感じました。
「ええ、寒いときはいつもこんな感じの服を着ています。」彼女は何気なく答えた。
彼女の返事に勇気づけられて、私はさらに調べてみました。「フード付きのフルボディスーツじゃないですよね? ちょっと見せてもらってもいいですか?」
彼女は澄んだ目で私を見つめ、うなずきました。「あなたは気付いたわね。でも、私がこんな格好をするのは、人を怖がらせないようにするためよ。」
それから彼女はマスクを下ろした。「これ外してほしかっただけでしょ?エアコンをこんなに高く設定すると息苦しいわ!」
現行犯で捕まった私は顔を赤らめた。彼女があまり話さなかったのも無理はない。瞬きしてもまつげの一部は動かなかった。彼女の顔はまるで衣料品店のプラスチックのマネキンのようだった。私はすぐに室温を22度に戻した。

「このマスクを外して見せてもらえますか?」私は彼女のあらゆる層の下にあるものが何なのかを知りたくてたまらなかった。
彼女は自分の顔を指差してこう答えた。「そんなことはあり得ません。私はあなたを知らないんです。」
彼女は少し考えた後、こう付け加えた。「あなたが悪い人ではないことはわかりますし、今日あなたがしてくれたことすべてには感謝しています。でも、私はそれを削除しません。ただアパートを見せてください。」
最後の部屋を案内し終えると、彼女が「まったく同じだ…」とつぶやくのが聞こえた。マスクと話し方のせいで、はっきりと聞き取れなかった。
リビングに戻ると、彼女はすぐにスミス氏に電話し、交渉もせずに彼の提示した値段に同意した。私はスミス氏が家賃に関していかにケチだったかを思い出し、腹が立った。
私はローラから電話を奪い取りました。ローラはぴったりしたボディスーツを着ていたので、しっかりと握ることができませんでした。そして受話器に向かって叫びました。「おい、おじいさん、そんな風にこの女の子を騙しちゃだめだよ!取り壊しの告知を4回も塗り直さなきゃならなかったんだ!この家がどれだけ長持ちするかなんて誰にも分からないよ。水漏れや電気系統のトラブルだらけなのに、本当に6万ドルの価値があると思うの?」
スミス氏は動揺しなかった。ローラにはすでに状況を伝えていたと説明した。売却の予定はなかったが、取り壊しの補償金はすでに支払われていたため、ローラが先にスミス氏に連絡してきたのだ。
私は驚いて、彼女に電話を返し、話を続けるように身振りで示した。
私は彼らに交渉を任せ、飲み物を飲みながらコンペのプレゼンテーションの準備を始めた。電話が終わると、彼女はマスクと手袋をはめて私に向き直った。「うまくいけば、明日にはこのアパートは私のものになります。できるだけ早く入居したいので…」
私はいらいらしながら彼女の言葉を遮った。「まずは契約書にサインして、それから話しましょう。それに、もしあなたが引っ越すとしても、少し時間をください。どうしてこの荒れ果てた家がこんなに人気があるんですか?」
彼女は真剣にうなずいた。「もちろん、時間はあげますよ。それと、先ほどはありがとう。この値段は喜んで払います。これが、長年この場所を大切にしてくださったスミスさんへの私なりの恩返しなのです。」
彼女にとってこの場所は何か特別な意味があるに違いないと思ったので、それ以上は尋ねませんでした。彼女がブーツを履こうとしたちょうどその時、彼女の電話がまた鳴りました。彼女は電話に出て私の住所を教え、申し訳なさそうに私に電話を渡しました。
「市の疾病管理センターです」と彼女はためらいながら言った。
電話の向こう側では、本日早朝に彼女の乗った飛行機の乗客がMERSと診断され、私たち2人とも15日間の隔離が必要だという声が聞こえた。
私は小声で悪態をついた。運が悪かっただけだ。