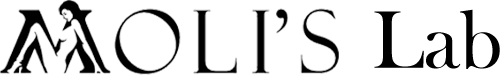記念日にウェディングドレス姿のヤオ
共有
「今日はヤオとの記念日なんだね…」
カレンダーを見ながら独り言を言った。
あれから何年も経ちましたが、あの日のことを思い出すだけで今でも胸がドキドキします。
今年は私たちが付き合い始めてちょうど5年目になります。
毎年、私たちはこの日を特別な日にしていますが、今回は少し違うことをするつもりです。
「よし…準備はできた。」
私は気を引き締めて部屋を出た。
「あら?どうしたの?すごく動揺しているみたいね」私が廊下に足を踏み入れると、ヤオは不思議そうに私を見ながら言った。
「いいえ、何でもないです」と私は答えました。
「へへ、本当?でも、仕事に行くのにすごく緊張しているように見えるよ。」
「え!? そう見えましたか……ははは……」
彼女の言うことはまさに的を射ていたので、私は苦笑いするしかなかった。
「きっと記念日にサプライズパーティーを準備してくれているんだと思ってたんだけど…」
彼女はいたずらっぽい笑顔でそう言った。
彼女は私のことを完全に見抜いていたようだ。
「まあ…それについては考えたんだけど…」
「ふーん…じゃあ何をするつもりだったの?」
ヤオは興味深げな表情で尋ねた。
"これ。"
「このドレスは…そしてこのマスクは…」
私がウェディングドレスと本物そっくりのシリコンマスクを披露すると、ヤオの顔は驚きで輝きました。
「あの時の撮影で着ていたドレスと同じデザインで、マスクもお揃いなんです。覚えていますか?」
「へへ、懐かしいな」
「うん、着てくれるといいなと思ってたんだけど…」
「素晴らしいですね、プロデューサー!」
ヤオは輝く笑顔を浮かべた。
「あの日はすごく楽しかったね。」
「うん…ヤオ、僕と一緒にいるとまだ幸せを感じる?」
「もちろんだよ!だって、僕は…」
そう言いながら、彼女はウェディングドレスの裾を持ち上げた。
「…運命の人と結婚しました。」
彼女は恥ずかしそうに、そしてうれしそうな笑顔でそう言った。
「へへ、嬉しいよ。」
彼女は話しながら私の手を握った。
「ヤオ、愛してるよ。」
「そして私もあなたを愛しています。」
私たちはお互いの目を見つめてキスをしましたが、どちらが始めたのかはわかりませんでした。
近づきすぎて、まるで体温がひとつになったような気がした。
これ以上幸せなことはないでしょう。
「プロデューサーさん、今すぐこのドレスとマスクを試着したいです。」
「わかりました。着替えてください。」
"わーい!"
そう言うと、彼女はドレスとマスクを着て自分の部屋に入って行きました。
数分後、ヤオが現れた。白いウェディングドレスをまとい、本物そっくりのマスクを完璧に着けた彼女は、何年も前の懐かしい姿に変身していた。そしてベッドサイドのテーブルから白いサテンの手袋を取り出し、それをはめた。滑らかな生地が彼女の手を包み込んだ。

「私の見た目はどうですか?」
彼女はくるりと回って私に見せ、手袋をした手をドレスの上に置いていました。
彼女の美しさはまるで地上に降り立った天使のようで、私は息を呑むほどでした。
「ヤオ、君は素敵だよ。」
「へへ、ありがとう!」
彼女は本当に喜んでいるようでした。
「本当に…とても美しい…」
「それは嬉しいですね!」
私はヤオを抱きしめた。
「プロデューサー……ん……」
今度は彼女も私を抱きしめ返し、サテンの手袋を私の背中に押し当てました。
「ん…ちゅぱ…れろ…んちゅ…」
私たちは情熱的にキスをしました。
「ん…ちゅぱ…ぷは…は…は…」
私たちの唇が離れると、唾液の糸が私たちの間に伸びました。
それが破れると、ヤオのマスクの下の呼吸が速くなり、彼女は私の股間に手を伸ばし、サテンの手袋で私のズボンを軽く撫でました。
「プロデューサーさん、もうこんな風になってるんですね…」
"ごめん…"
「大丈夫。それだけ私のことを望んでいるってことでしょ?」
"はい…"
「記念日だから今日は頑張ろうと思います。」
「どうぞ」
そうして、私たちはベッドに向かいました。

彼女は私のズボンを脱がせて、テントのような下着の上から手袋をした手で私を撫でました。
「暑くなってきましたね。」
「ヤオは美しすぎるからだよ…」
「あぁ……そんな目で言われると顔が赤くなっちゃう」
ヤオはマスク越しに恥ずかしそうに、お茶目な笑みを浮かべた。
「いいえ、本当です。結婚した時からそう思っていました。いや、初めて会った日からそう思っていました。」
「ああ……そんなふうにおだてても、何も得しないよ?」
「お前の全てが欲しいんだ、ヤオ。」
「まあまあ……プロデューサーさん、本当に情熱的ですね」
彼女の声には興奮の兆しが感じられた。
「でも、私のすべてはすでにあなたのものです…だから、あなたは私に何をしてもいいんです。」
「じゃあ…あの…手コキ…」
「プロデューサーさん、このドレスとマスクはそのためだけに買ったんですか?」
「いえ!偶然ですよ!」
純粋にヤオを喜ばせるために買ったのに、彼女に私の欲望を見抜かれて恥ずかしい思いをした。
「そうなんですか?まあ、それなら仕方がないですね。」
そう言うと、彼女はゆっくりと私の下着を下ろし、サテンの手袋が私の肌をかすめました。
私の勃起は自由になりました。
「わぁ、元気いっぱいですね!」
ヤオは楽しそうに笑った。
「なんかかわいいですね!」
彼女は手袋をした両手で私を優しく掴みました。サテンの手袋が私の肌を滑らかに撫でました。
「あぁ……」
完全に勃起した状態でも、私の控えめなペニスは彼女の小さな手に簡単に収まりました。
「ふふ、ピクピクしたよ。」
彼女は手を上下に動かし始めました。
「あぁ…気持ちいい。」
"私は嬉しい。"
シーッ、シーッという音とともに、喜びの波が高まっていった。
先走り液が自由に流れ出て、彼女の手袋を濡らした。
「ふふ、プロデューサーさんのペニスからは汁がたくさん出ていますよ。」
「ごめんなさい、もうすぐイっちゃうかも…」
「いいですよ。いつでも出してください。」
「はい……あぁ……!」
彼女の手袋をした指が、包皮から覗く亀頭を撫でたとき、私は哀れな声をあげた。

「ここ気持ちいいだろう?」
彼女はその敏感な部分に集中し、サテンの手袋で優しく刺激した。
私は快感で膝が折れないように必死に抵抗しました。
「あなたのペニスはいやらしい匂いがし始めていますよ。」
露出した先端の開口部の周囲には黄色っぽい垢が付着していた。
ヤオは顔を近づけ、マスク越しに匂いを嗅ぎ、そして舐め取った。
「塩辛くて美味しい。」
「ヤオ…それは…いや…」
"なぜだめですか?"
「だって…すぐイっちゃうから…」
「大丈夫ですよ。プロデューサーさんに汚してもらっても嬉しいですよ」
ヤオはマスクをした頬をそれにこすりつけた。
「だから、我慢しないで、吐き出してください!」
「ヤオ……」
「あなたは一生懸命頑張ってきたので、あなたのペニスには精液と恥垢がたくさん溜まっているでしょう?」
「あ、うん……」
「全部私が引き取ってあげるよ」
そう言うと、彼女は柔らかくなった包皮を引き下げて亀頭を露出させ、手袋が少しずれた。
重度の包茎のため、未発達でピンク色の亀頭(ほぼ処女)には厚い層の恥垢が固まっていた。
「たくさん貯め込んでるね。」
ヤオはサテンの手袋で私の乱れたペニスを愛撫した。その布地はかすかに汚れていた。
「あぁ……ヤオ……」
「プロデューサー、覚えていますか?私が初めてあなたのことを手でシゴいた時のことを?」
"はい…"
どうして忘れられるのでしょう?
それ以来、私は彼女の手に魅了されてきました。
「あの日のことを思い出すだけで、今でも体が熱くなります。」
"私も…"
「大切な記念日です。私たちの結婚、初めてのキス、手を繋いだこと、そして初めてあなたを撫でたこと、すべてこの日です。」
"うん…"
「あの時と同じ手で、今度はこのサテンの手袋で、あなたのペニスを気持ちよくさせてあげるから、いっぱい射精して。」
白いドレスとマスクを着けた女神が私に微笑みかけました。
同時に、彼女の熟練した手コキは私の弱々しい小さなペニスの弱い部分を狙っていました。
「あぁ……!ん……!」
「さあ、もっとリラックスしないと、うまくいきませんよ。」
「ダメだ…!そんなことされたら…我慢できない…!」
「大丈夫だよ。遠慮しなくていいよ」
「じゃあ…手袋の中…!」
「はい、分かりました。」
ヤオはサテンの手袋を片方剥がして私の短いペニスに滑り込ませた。滑らかな生地が私を包み込んだ。
「あぁ…来る…!」
「はい、どうぞ。」
「うううううう!!!!」
噴出!飛び散る!
黄色っぽい精液がサテンの手袋に詰まっていた。
「いっぱい出たよ♪」
脈打つたびに大量の精液が噴き出し、布地の中に溜まった。
それが尿道を駆け抜ける感覚で背筋が震えました。
「まだ止まらないんだね?」
"ごめん…"
「謝らないでください。これは私の手の中で仕事をうまくこなしたことに対する名誉の印です。」
「プロデューサーさんのペニス、ちゃんとイっててよかったね。」
ヤオは残った手袋をした手で私を優しく撫でた。
その心地よさのせいで、私は永遠にその瞬間に留まりたいと思いました。

手袋が精液で溢れかえると同時に、私の絶頂は収まり、縮んだペニスから少しだけ精液が漏れ出しました。
「たくさん漏らしたね。」
ヤオは手袋を外して、話しながら中を覗き込んだ。
彼女は、中に溜まった濃い黄色がかった粘液を愛おしそうに見つめた。
「わぁ…すごい量だ…」
「恥ずかしいです…」
「そして、とても強い匂いがする…」
ヤオは夢見るような表情でサテンの手袋を弄び、それからそれを口に運び、マスクの隙間から舐めた。
「それはとても素晴らしい…」
彼女はそれを舐めてきれいにした。サテンは唾液で光っていた。
「プロデューサーの…」
ヤオは手袋に残った汁をズルズルと吸い取り、口を開けてマスク越しに私に見せた。
「全部飲んだの!?」
「はい♪」
彼女はマスクのせいで声が少しくぐもったが、至福の笑顔で答えた。
「よかったですか?」
「うん、なんか今日は精液がいつもより美味しく感じるよ」
ヤオは私を強く抱きしめた。
私は彼女の胸の柔らかさと温かさを感じました。
「特別な日に運命の人からもらったからかな?」
「きっとそうだよ」
「僕もだよ。僕たちはずっと一緒だよ。」
"はい。"
私たちは再びキスをしたが、どちらが始めたのかもわからなかった。
私たちは長い間、そんなふうに抱き合っていました。